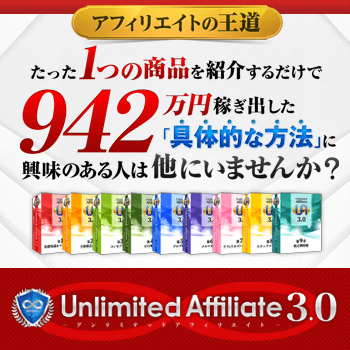無料ブログは基本的には削除されにくいと
言われますが、ゼロではありません。
実際に ゲームアプリ案件(GAME FRAT取扱) に特化したサイトを
シーサーブログで運用し、5か月後に削除 された体験をまとめます。
集客はTwitterが中心で、Twitterアカウント自体は無傷のまま残ったものの、
着地点のブログが消えることで一気に収益が途絶えた教訓を共有します。
はじめに:無料ブログは「基本的には削除されない」が、リスクはゼロではない
シーサーブログ(Seesaa Blog)は長年アフィリエイターに
使われてきた無料ブログで、
ガイドラインを守って運用すれば基本的には削除されない
というのが一般的な見方です。
とはいえ、無料サービスはプラットフォーム側の裁量が強く、
機械的なチェックや通報を契機に突如として削除が
起こりうる点は常に意識しておく必要があります。
構成と狙い:GAME FRAT案件に特化したゲームアプリを紹介するサイト作成
対象サイトは、GAME FRATで取り扱っているゲームアプリ案件を
中心にレビュー・簡易攻略・インストール誘導を行う
縦長ランディング型の構成でした。
初期は更新頻度を重視し、1〜2日に1本の短め記事を積み上げ、
検索は二の次で即効性のあるSNS流入をメインに設計していました。
集客チャネル:Twitter経由がメイン
新規のTwitterアカウントを立ち上げ、
ゲーム好きのユーザーと交流しながら
記事リンクを流す運用です。
アプリの配信開始やイベント開催などニュース性の高いタイミングで
ツイートを重ねることで、クリック率は安定。
フォロワー増とともに成果が発生し、
当初の想定どおりSNS→ブログ→案件の導線が機能していました。
転機:運営開始から5か月でブログが突然の削除
順調に見えた矢先、5か月目に管理画面へログインできなくなり、
公開ページも404相当の状態に。
Twitterアカウントは問題なく利用でき、
警告も凍結もありませんでした。
つまり集客口は無傷のまま、着地点であるブログだけが消えた形です。
結果として流入は宙に浮き、収益は即時にストップしました。
問い合わせ:シーサーブログ側からの回答はなし
サポートフォームから経緯を詳細に伝えましたが、
具体的な回答は得られませんでした。
ガイドライン違反・通報・自動判定など可能性は複数考えられるものの、
無料サービスゆえに審査プロセスや
判定基準の詳細が開示されないのは珍しいことではありません。
考えられる要因(推測)
- 広告性の強さ:誘導色が強い記事構成やリンク比率が自動判定でリスクと見なされた可能性。
- 外部リンクの集中:短期間で同種リンクが増え、スパム的と判定された可能性。
- 通報:競合やユーザーからの通報がトリガー。
- 素材・表現:画像や文言が規約のグレーを跨いだ可能性。
いずれも確証はなく、無料ブログには削除リスクが常にある
ことだけが明確に残りました。
無料ブログ運用のリスクと限界
無料ブログは初期費用ゼロ・環境構築不要という
大きなメリットがある一方、
コントロール不能な削除リスクが最大の弱点です。
とくにアフィリエイトのように広告性が高いサイトは、
同一ジャンルの増加や通報の影響を受けやすく、
健全に運用していても突然のサービス側判断で
資産を失う可能性を避けられません。
ダメージを最小化するための対策
- 独自ドメイン+自前CMS(WordPress等)へ早期移行
収益の柱は自前の土台で。 - 記事バックアップの常態化
原稿・画像・内部リンク構造を定期エクスポート。 - ディストリビューションの多層化
Twitter, メルマガ, 他SNSで複数の着地点を用意。 - 表現・導線の健全化
誤認を招く表現・過剰な煽り・広告比率の偏りを是正。 - 運用ログの記録
更新履歴・画像出典・問い合わせ履歴を残す。
まとめ:学びと今後の運営方針
今回のケースから得られた教訓は明確です。
無料ブログは学習と検証の場としては優秀ですが、
収益の中核を担わせるには不安定です。
集客の起点であるTwitterは無傷でも、
受け皿が消えれば結果はゼロに戻る。
だからこそ、早い段階で独自ドメイン+自前環境にシフトし、
バックアップと配信経路の多層化で
単一障害点(SPOF)を取り除くことが、
安定運営の最短ルートだと考えます。