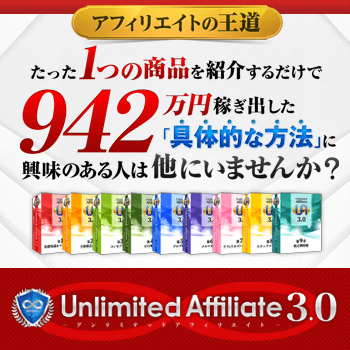Webで「読まれる・信頼される」記事づくりの指針が
E-E-A-T(Experience/Expertise/Authoritativeness/Trust)。
検索だけでなく、SNSやブックマークでも
「誰が、どの立場で、どの根拠で書いたのか」を示すことが重要です。
本記事は初心者向けに、概念のやさしい解説から記事と
サイトでの実装手順までをまとめた実務ガイドです。
E-E-A-Tの基本:4要素を一言で
- Experience(経験)
実際にやってみた/使ってみた/行ってみた等の体験にもとづく一次情報。 - Expertise(専門性)
分野の知識・技能の深さ。正確性・用語の使い方・データの扱い方に現れる。 - Authoritativeness(権威性)
外部からの評価・推薦・被リンク・掲載実績・肩書など、周りが認める力。 - Trust(信頼性)
運営の透明性・実名/連絡先・根拠提示・誤り訂正・安全性(https/広告表記等)。
4要素のうち最終判断はTrust(信頼性)。
どれだけ詳しくても、情報の出どころや運営が不透明なら評価は伸びません。
なぜ今E-E-A-Tが重要なのか
検索の上位には「答えが早くて正確」「誰が書いたかが明確」な記事が選ばれます。
特に投資・金融・健康・法律など生活に影響が大きいテーマでは、
実体験+根拠の両立が欠かせません。
E-E-A-Tはアルゴリズムの魔法ではなく、
読者にとって安心できる設計を言語化したものです。
記事レベルでの実装:今日からできる10チェック
- 筆者の立場を明記(投資家/運営者/利用者/専門家/取材者など)。
- 体験の具体(Experience):日時・場所・使用条件・比較対象・失敗談も。
- 一次ソースへのリンク:公的統計・公式リリース・法令・金融機関ページ。
- 独自の検証手順:評価軸・測定方法・サンプル数・限界の明記。
- 反証可能性:他説・反対意見・注意点も併記。
- 利益相反の表示:アフィリエイト/PR/提供の有無を冒頭と末尾で明示。
- 更新履歴:公開日/最終更新日/修正点を記事末に。
- 誤りの訂正窓口:問い合わせリンク・Xフォーム・メール。
- 可読性:見出し階層・表/箇条書き・要約ボックスでスキャンしやすく。
- 画像の根拠:自作or出典記載。代替テキスト(alt)も適切に。
サイト/運営レベルでの実装:土台を固める7項目
- 運営者情報(プロフィール・実績・連絡先・所在地)。
- 編集ポリシー(取材基準・引用ルール・広告方針)。
- 監修体制(専門家レビュー/ダブルチェックの流れ)。
- セキュリティ(https、プライバシーポリシー、クッキーバナー)。
- スキーマ(Article/Review/FAQ/Person/Organizationなどの構造化データ)。
- 外部評価(掲載実績、受賞、外部登壇、被リンク獲得の施策)。
- UX/速度(Core Web Vitals、広告の表示バランス、スマホ最適化)。
テンプレ:E-E-A-Tを満たす記事冒頭(例)
【結論】N社とS社を実機で3週間比較した結果、長期の積立投資なら手数料が低いS社を推奨します。 根拠:①実測コスト ②約款比較 ③サポート対応。筆者は投資歴7年(個人ではNISA/企業では運用部のサポート経験)。 評価手順と限界:バックテストは過去5年・データは公表値を採用、暴落局面の再現性は未検証。
冒頭で結論・根拠・筆者の立場・方法の限界を示すと、信頼の初速が上がります。
NG例:E-E-A-Tを損なう典型パターン
- 匿名・連絡先不明・運営者ページなし。
- 体験談が抽象的(「すごい」「神」だけ)。
- 根拠リンクが匿名ブログ/引用元不明の画像。
- 誤情報の指摘を無視。更新日が数年前のまま。
- アフィリンクのみ大量設置で、比較・注意点がない。
効果測定:信頼は「行動」で可視化できる
- 滞在時間/スクロール深度:結論前離脱が減れば読みやすく改善。
- ブランド検索:「サイト名+キーワード」の増加は権威性の兆候。
- 被リンク/メンション:自然言及や引用が増えているか。
- 直帰率とCTA達成率:信頼が高いとクリック/問い合わせが伸びる。
実装ロードマップ:1週間で土台を作る
- Day1:運営者情報・編集ポリシーを公開。
- Day2:記事テンプレに「結論→根拠→体験→注意点→更新履歴」を組み込む。
- Day3:主要記事に一次ソースリンクとFAQを追加。
- Day4:構造化データ(Article/FAQ/Review/Person)を適用。
- Day5:監修フローを整備(レビュー依頼→修正→公開)。
- Day6:誤情報指摘フォーム設置、プライバシーポリシー更新。
- Day7:実績ページ作成(掲載/登壇/受賞/被リンク事例)。
まとめ:E-E-A-Tは“好かれる設計図”
E-E-A-Tはテクニックではなく、読者に誠実な作法を要件化したもの。
体験に裏打ちされた情報を、根拠とともに、誰が書いたかを明確に示す。
これを記事とサイトの両面で積み重ねれば、
検索・SNS・口コミのすべてで「また読みたい」という評価につながります。
今日からできるチェックから一つずつ実装していきましょう。