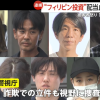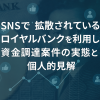⚠️ 物件価格以上の融資 ⚠️
不動産オーバーローンの
リスクと注意点
資金調達で失敗しないために知っておくべきこと【2025年版】
不動産投資や事業資金の調達において
「オーバーローン」という言葉を耳にする方は少なくありません。
通常、不動産ローンは購入する物件価格と
同等もしくはそれ以下の融資が基本です。
しかしオーバーローンとは、物件価格以上の資金を
金融機関から借り入れることを指します。
表面上は魅力的な資金調達方法に思えるかもしれませんが、
実際には数多くのリスクが潜んでいます。
本記事では、オーバーローンの仕組み、リスク、注意点、
そして失敗しないための判断基準を徹底解説します。
⚠️ 重要な注意事項
本記事は、不動産オーバーローンのリスクについて
一般的な情報提供を目的としています。
オーバーローン自体は違法ではありませんが、
虚偽申告や書類偽造などの不正行為は違法です。
不動産投資や資金調達を検討する際は、必ずリスクを理解し、
専門家に相談のうえ慎重に判断してください。
オーバーローンとは何か?
基本的な仕組み
通常の不動産ローンでは、融資額は物件価格の80~100%程度が一般的です。
例えば、3,000万円の物件を購入する場合、融資額は2,400万円~3,000万円となります。
📊 通常のローンとオーバーローンの違い
✅ 通常のローン(物件価格3,000万円の場合)
融資額:2,400万円~3,000万円(物件価格の80~100%)
自己資金:0円~600万円
❌ オーバーローン(物件価格3,000万円の場合)
融資額:3,500万円~4,000万円(物件価格を500万円~1,000万円上回る)
手元に残る現金:500万円~1,000万円(物件購入後)
💡 オーバーローンが可能になる仕組み
1. 物件価格を水増しする
実際の物件価格よりも高い売買契約書を作成し、
金融機関に提出することで、物件価格以上の融資を引き出します。
これは違法行為です。
2. リフォーム費用を上乗せする
実際には行わないリフォーム工事の費用を融資額に含めることで、
手元に現金を残します。これも不正行為です。
3. 諸費用を融資に含める
登記費用、仲介手数料、保険料などの諸費用を融資額に含めます。
これ自体は合法ですが、総額が物件価格を大きく上回ることになります。
属性が良ければ一見お得に見える仕組み
銀行やノンバンクは、申込者の年収や勤務先、
資産状況といった「属性」を重視します。
📋 金融機関が重視する「属性」
- 年収:500万円以上が目安(高いほど有利)
- 勤務先:上場企業、公務員などが有利
- 勤続年数:3年以上が望ましい
- 資産状況:預貯金、株式、不動産などの保有
- 信用情報:過去の借入や返済の履歴
✨ 属性が高いと可能になること
- 物件価格以上の借入が可能
- 手元に現金を残したまま投資用不動産を取得
- 初期投資を抑えて複数物件を所有
- 低金利での融資
これにより、不動産投資家にとっては一見魅力的に映ります。
⚠️ しかし忘れてはいけないこと
借入金は返済義務のある負債であり、
将来的な収支シミュレーションを慎重に行わなければ、
資金繰りの悪化を招く可能性が高まります。
リスク1:ブローカーに手数料で大きく損をする可能性
💸 ブローカー手数料の実態
オーバーローンを組む場合、金融機関と直接交渉するのではなく、
不動産ブローカーや仲介業者を通じて話が進むケースが少なくありません。
ブローカーが介在することによる問題
- 高額な手数料:融資額の3~10%という莫大な成功報酬
- 不透明な費用:何に対する費用かが不明確
- 複数の中間業者:ブローカーがさらに別の業者に依頼し、手数料が膨らむ
📊 具体例:融資額4,000万円の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 融資額 | 4,000万円 |
| 物件価格 | 3,000万円 |
| 手元に残る(融資額 – 物件価格) | 1,000万円 |
| ブローカー手数料(融資額の5%) | -200万円 |
| 不動産仲介手数料 | -100万円 |
| 登記費用・諸費用 | -100万円 |
| 実際に手元に残る現金 | 600万円 |
💡 せっかく1,000万円を手元に残したつもりが、
実際には600万円しか残らず、400万円が手数料として消えてしまいます。
一部の業者は「資金調達のノウハウ」を強調し、
融資額の数%という莫大な成功報酬を要求します。
結果的に、せっかく残した手元資金が
ほとんどブローカーの利益として消えてしまい、
投資家自身が損をするケースが後を絶ちません。
短期的には資金が増えたように見えても、
長期的には大きな負担となるのです。
リスク2:サブリース契約があっても安心できない理由
🏢 サブリース契約とは?
投資用不動産では、空室リスクを軽減するために
「サブリース契約」がセットで提案されることが多くあります。
サブリースの仕組み
不動産管理会社がオーナーから物件を一括で借り上げ、
入居者に転貸(サブリース)します。
オーナーには空室の有無に関わらず、一定の家賃保証が支払われます。
✅ サブリースのメリット(表面上)
- 空室リスクの軽減
- 家賃保証による安定収入
- 管理業務の委託
一見すると安心材料のように感じられるでしょう。
❌ サブリースの実態とリスク
- 数年後に保証賃料が減額される
契約更新時に「周辺相場が下がった」などの理由で家賃を減額 - 契約解除のリスク
管理会社側から一方的に契約を解除される可能性 - 修繕費用は別途請求
原状回復費用や修繕費用はオーナー負担 - 免責期間
入居者退去後1~3ヶ月は家賃保証がない - 不透明な入居状況/*-
実際の入居者や家賃がオーナーに開示されない
サブリースだからといって安定収入が保証されるわけではなく、
むしろオーバーローンの高額返済と合わさって、
経営が一気に苦しくなる可能性があるのです。
📊 具体例:サブリース契約の収支悪化
| 期間 | 保証家賃(月額) | ローン返済(月額) | 収支 |
|---|---|---|---|
| 1~2年目 | 10万円 | 12万円 | -2万円 |
| 3~5年目(減額後) | 8万円 | 12万円 | -4万円 |
| 6年目以降(さらに減額) | 6万円 | 12万円 | -6万円 |
💡 当初は月2万円の赤字でしたが、保証家賃が減額されるにつれて
赤字幅が拡大し、毎月6万円の持ち出しになります。
年間で72万円の赤字、10年で720万円の損失です。
リスク3:不動産価値が低いため売却リスクが高い
不動産を担保に借入を行っている以上、
最終的な出口戦略は売却です。
⚠️ オーバーローンの場合の問題
オーバーローンの場合、物件価格以上の借入をしているため、
万が一の際に売却してもローン残債を
全て返済できないケースが少なくありません。
- 売却価格 < ローン残債 → 赤字
- 差額を自己資金で補填しなければならない
- 自己資金がなければ売却できない
📉 資産価値が目減りしやすい物件
特に以下のような物件は、購入直後から資産価値が目減りする傾向にあります。
- 新築ワンルームマンション:購入直後に価格が20~30%下落
- 地方の収益物件:人口減少により需要が低下
- 築古物件:老朽化により価値が下がる
- 駅から遠い物件:立地が悪く買い手がつかない
📊 具体例:売却時の赤字
購入時(新築ワンルームマンション)
| 物件価格 | 3,000万円 |
| 融資額(オーバーローン) | 3,500万円 |
5年後(売却時)
| 売却価格 | 2,200万円 |
| ローン残債 | 3,200万円 |
| 不足額(自己資金で補填) | -1,000万円 |
💡 急な売却が必要になった場合、
「買い手が見つからない」「売れても大幅な赤字」
といった事態に直面することが多いのです。
1,000万円を自己資金で補填できなければ、売却すらできません。
リスク4:毎月の返済額が重くのしかかる
オーバーローンを利用すると、当然ながら借入総額が増えるため、
毎月の返済額も高額になります。
📊 通常のローンとオーバーローンの返済額比較
前提条件:物件価格3,000万円、金利2.0%、返済期間35年
| ローンの種類 | 融資額 | 月額返済 | 総返済額 |
|---|---|---|---|
| 通常のローン(100%) | 3,000万円 | 約10万円 | 約4,200万円 |
| オーバーローン(117%) | 3,500万円 | 約11.7万円 | 約4,900万円 |
| 差額 | +500万円 | +約1.7万円 | +約700万円 |
💡 毎月1.7万円の差額は年間で約20万円、35年で約700万円の追加負担となります。
⚠️ 返済が滞るリスク
安定した家賃収入や給与収入があるうちは問題がないように思えますが、
以下のような要因により返済が滞るリスクは常に存在します。
- 空室の発生:家賃収入が途絶える
- 修繕費用の発生:予期せぬ出費
- 金利上昇:変動金利の場合、返済額が増える
- 給与収入の減少:転職、リストラ、病気など
- サブリース契約の減額・解除:保証家賃が減る
💔 最悪のシナリオ
不動産投資は本来、長期的に安定した収益を狙うものですが、
オーバーローンによる返済負担はキャッシュフローを圧迫し、
最悪の場合は自己破産に追い込まれるケースもあります。
- 返済が滞る → 督促状が届く
- 延滞が続く → ブラックリストに載る
- 競売にかけられる → 市場価格より安く売却
- 残債が残る → 自己破産
オーバーローンの法的問題
⚖️ オーバーローンは違法か?
結論:オーバーローン自体は違法ではない
諸費用を含めて物件価格以上の融資を受けることは、
金融機関が認めれば合法です。
❌ しかし、以下の行為は違法
- 虚偽の申告:収入や資産を偽って申告 → 詐欺罪(刑法246条)
- 書類の偽造:売買契約書や収入証明書を偽造 → 私文書偽造罪(刑法159条)
- 物件価格の水増し:実際より高い価格で契約書を作成 → 詐欺罪
- 不正な融資斡旋:違法な融資を斡旋 → 貸金業法違反
⚠️ リスク
不正な方法でオーバーローンを組んだ場合、
金融機関から一括返済を求められる可能性があります。
また、ブローカーから「大丈夫」と言われても、
最終的な責任は借り入れた本人が負います。
オーバーローンで失敗しないために
✅ 慎重に判断するためのチェックリスト
1. 収支シミュレーションを行う
- 家賃収入、ローン返済、管理費、修繕費などを詳細に計算
- 空室率、金利上昇、家賃下落などのリスクも考慮
- 最悪のシナリオでも返済できるか確認
2. ブローカーの手数料を確認
- 手数料の内訳を明確にしてもらう
- 複数の業者から見積もりを取る
- 直接金融機関と交渉できないか確認
3. サブリース契約の内容を確認
- 保証家賃の減額条件を確認
- 契約解除の条件を確認
- 免責期間の有無を確認
- 修繕費用の負担割合を確認
4. 物件の資産価値を確認
- 周辺の中古物件の相場を調べる
- 新築の場合、購入直後の価格下落を想定
- 売却時のローン残債との差額を計算
5. 専門家に相談
- 不動産コンサルタント
- ファイナンシャルプランナー(FP)
- 税理士
- 弁護士(契約内容の確認)
🚨 こんな勧誘には要注意
- 「絶対に儲かる」と断言する
- 「今すぐ決めないと」と急かす
- 「特別なノウハウ」を強調する
- 手数料の内訳が不明確
- 契約書をよく読ませない
- リスクを説明しない
これらに該当する場合、詐欺や悪質な勧誘の可能性があります。
契約は絶対にしないでください。
健全な不動産投資の選択肢
オーバーローンのリスクを避け、健全に不動産投資を行うには、
以下のような選択肢があります。
1. 自己資金を増やしてから投資する
頭金を多めに用意することで、借入額を減らし、毎月の返済負担を軽減できます。
目安として、物件価格の20~30%の自己資金があると安心です。
2. 価格が適正な物件を選ぶ
新築プレミアムが乗っていない中古物件や、
立地が良く資産価値が下がりにくい物件を選びましょう。
4. REIT(不動産投資信託)を活用
大きな借金を背負わずに、少額から不動産投資の恩恵を受けられます。
流動性も高く、いつでも売却できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. オーバーローンとは何ですか?
A. 物件価格以上の資金を金融機関から借り入れることを指します。
通常、不動産ローンは購入する物件価格と同等もしくはそれ以下の融資が基本ですが、
オーバーローンでは物件価格を上回る融資を受けます。
例えば、3,000万円の物件に対して3,500万円の融資を受けるケースです。
Q2. オーバーローンのリスクは何ですか?
A. 主なリスクは、ブローカーによる高額手数料、サブリース契約の不安定さ、
不動産価値の低さによる売却時の赤字、毎月の返済額の重さです。
最悪の場合、自己破産に追い込まれるケースもあります。
また、不正な方法でオーバーローンを組んだ場合は、
金融機関から一括返済を求められる可能性もあります。
Q3. オーバーローンは違法ですか?
A. オーバーローン自体は違法ではありません。しかし、金融機関を欺く行為は違法です。
諸費用を含めて物件価格以上の融資を受けることは、金融機関が認めれば合法です。
しかし、虚偽の申告(収入や資産を偽る)、書類の偽造(売買契約書や収入証明書を偽造)、
物件価格の水増しなどは詐欺罪や私文書偽造罪に該当する可能性があります。
Q4. ブローカーの手数料はどのくらいですか?
A. 融資額の3~10%という高額な成功報酬を要求されるケースが多いです。
例えば、4,000万円の融資を受ける場合、
5%の手数料であれば200万円がブローカーに支払われます。
手数料の内訳が不明確な場合も多く、注意が必要です。
Q5. サブリース契約は安全ですか?
A. サブリース契約には多くのリスクがあり、安全とは言えません。
数年後に保証賃料が減額されるケース、契約解除のリスク、
修繕費用の別途請求、免責期間の存在など、様々な問題があります。
「家賃保証」と言っても、永久に保証されるわけではありません。
Q6. オーバーローンで失敗しないためにはどうすればいいですか?
A. 慎重な収支シミュレーション、ブローカー手数料の確認、
サブリース契約の詳細確認、物件の資産価値の確認、専門家への相談が重要です。
特に、最悪のシナリオ(空室、金利上昇、家賃下落など)でも
返済できるかどうかを慎重に検討してください。
短期的な手元資金の増減に惑わされず、
長期的なリスクと収支を見極めることが重要です。
Q7. 新築ワンルームマンションはオーバーローンで買っても大丈夫ですか?
A. 新築ワンルームマンションは特に危険です。
新築ワンルームマンションは購入直後に価格が20~30%下落する傾向があります。
オーバーローンで購入すると、売却時に大幅な赤字になる可能性が非常に高いです。
また、サブリース契約とセットで販売されることが多く、
複合的なリスクがあります。
Q8. オーバーローンで返済が苦しくなったらどうすればいいですか?
A. 早めに専門家に相談してください。
相談先:金融機関(返済計画の見直し)、弁護士(債務整理、自己破産)、
ファイナンシャルプランナー(家計の見直し)、不動産コンサルタント(売却相談)。
延滞が続くとブラックリストに載り、競売にかけられる可能性があります。
早期の対応が重要です。
まとめ:リスクを理解した上で冷静な判断を
不動産のオーバーローンは、資金調達の一手段として活用できる反面、
非常に大きなリスクを伴います。
主なリスク:
- ブローカーによる手数料損失:融資額の3~10%が手数料として消える
- サブリース契約の不安定さ:数年後に保証賃料が減額、契約解除のリスク
- 不動産価値の低さ:売却時に赤字、残債を自己資金で補填
- 毎月の返済額の重さ:借入総額が増え、キャッシュフローを圧迫
- 自己破産のリスク:返済が滞ると最悪の場合、自己破産
重要なポイント:
- 属性が高ければ融資は通りやすいが、借入金は返済義務のある負債
- 短期的な手元資金の増減に惑わされず、長期的なリスクを考慮
- 将来的なリスクと収支シミュレーションを十分に行う
- 専門家に相談し、冷静に判断する
不動産投資を検討する際は、短期的な手元資金の増減に惑わされず、
将来的なリスクと収支シミュレーションを
十分に行ったうえで冷静に判断することが重要です。
関連記事
⚠️ 免責事項
本記事は、不動産オーバーローンのリスクについて
一般的な情報提供を目的としており、
特定の金融機関や不動産業者を批判・推奨するものではありません。
オーバーローン自体は違法ではありませんが、
虚偽申告や書類偽造などの不正行為は違法です。
不動産投資や資金調達を検討する際は、必ずリスクを理解し、
専門家(ファイナンシャルプランナー、税理士、弁護士など)に
相談のうえ慎重に判断してください。
本記事の内容に基づく行動によって生じたいかなる損害についても、
当サイトは責任を負いかねます。
記事に関するご質問やご意見は、sophisticatedinvestors.tokyo までお寄せください。