前編「【超入門】NISAの始め方」の続編です。
この記事では、実際の銘柄(種類)と積立金額の決め方を、
30〜40代のサラリーマン向けに“今日すぐ設定できるレベル”まで落とし込みます。
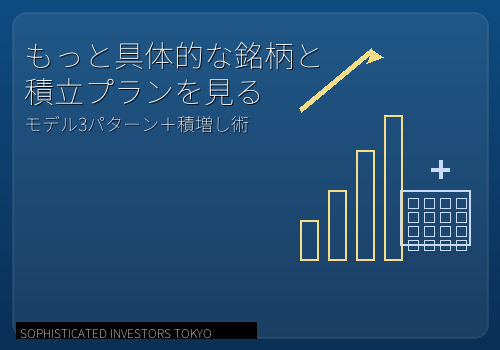
前提と方針:長期・分散・低コストに“作業の少なさ”を足す
- 長期:10年以上を基本。値下がり局面でも売らない設計に。
- 分散:国・業種・通貨に分散。一つのテーマへ集中しない。
- 低コスト:信託報酬は可能なら年0.10%前後を目安に。
- 作業の少なさ:銘柄数は最小限、自動積立+年1回だけ点検。
ポートフォリオ3モデル(つみたて投資枠が中心)
Model A:超保守(迷ったらコレ)
全世界株式インデックス1本(100%)。地理も業種も自動で分散され、
乗り換えの手間が最少。為替も各国に分散されます。
- 対象例:全世界株式(オールカントリー型など)
- 想定コスト:年0.10%前後
- メリット:1本で完結、メンテが楽
- 留意点:米国の比率が高め(世界時価総額比)
Model B:標準(米国強め×世界分散)
米国株式+全世界株式で“世界の成長を取りつつ米国を厚め”に。
- 配分:米国株式60%、全世界株式40%
- 対象例:S&P500 or 米国広範インデックス/全世界株式
- 想定コスト:年0.09〜0.15%
Model C:積極(先進国中心+新興国を少量)
ややリスク許容度が高い方向け。先進国中心に、新興国を10%以内でスパイス。
- 配分:先進国株式80%、新興国株式10%、国内株式10%
- 対象例:先進国(日本除く)/新興国指数/国内TOPIX
※具体的なファンド名は各社の「低コスト・インデックス」を選択。
純資産総額の増加傾向、信託報酬、トラッキング誤差をチェック。
積立金額の決め方(2万円/3万円/5万円)
生活防衛資金(6ヶ月分)がある前提で、続けられる最小額から開始 → 半年ごとに増額が現実的です。
| 毎月額 | 設定例(Model B) | ボーナス増額 |
|---|---|---|
| 2万円 | 米国株1.2万円/全世界0.8万円 | 年2回×各3万円 |
| 3万円 | 米国株1.8万円/全世界1.2万円 | 年2回×各5万円 |
| 5万円 | 米国株3万円/全世界2万円 | 年2回×各7万円 |
※金額は一例。給与日直後に自動積立、ボーナス月は“上乗せ”で。
年1回のリバランス(正解は“触りすぎない”)
- 年末に資産配分を確認(証券会社のポートフォリオ機能でOK)。
- 配分が±5%を超えたら、翌年の積立比率を調整(売却より“買いで戻す”)。
- 大きく崩れたときだけ部分売却で均す(税制上の非課税は維持)。
売買頻度が増えるほど「高値掴み/安値売り」の癖が出ます。“年1回だけ見る”がむしろ最適。
暴落時の“積み増しルール”を決めておく
- 基準:基準価額が直近高値から-10%/-20%のとき、増額スイッチ。
- 方法:通常積立に+5,000〜1万円を3ヶ月限定で上乗せ。
- 目的:値下がり期に口数を多く買い、回復時の伸びを狙う。
感情で動くと逆効果。「数値で決めたら自動」がコツです。
コスト最適化チェック(始める前に3つだけ)
- 信託報酬:年0.10%台を目安に比較。
- つみたて設定:毎月だけでなく「毎週/毎日」も選べるか。
- ポイント還元:保有残高に対する年率還元があると実質コスト低下。
設定の実行手順(5分で完了)
- 証券会社アプリで「つみたて投資枠」を選ぶ
- Model A/B/Cのいずれかを選び、対象インデックスを検索
- 毎月額と積立日(給料日直後)、ボーナス増額を入力
- つみたて対象の再投資型を確認して保存
- メモに「年1回点検」「下落時の増額ルール」を記入
ざっくり将来試算(過度な期待はしない)
長期平均の年率を3%/5%/7%で粗く試算すると…(税・手数料は単純化)。
| 毎月額 | 20年・3% | 20年・5% | 20年・7% |
|---|---|---|---|
| 2万円 | 約657万円 | 約825万円 | 約1,045万円 |
| 3万円 | 約986万円 | 約1,237万円 | 約1,567万円 |
| 5万円 | 約1,643万円 | 約2,062万円 | 約2,612万円 |
※実際のリターンは上下します。積立を止めない仕組みと、生活防衛資金の確保が最優先。




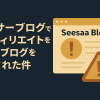

[…] もっと具体的な銘柄と積立プランを見る […]