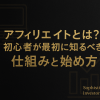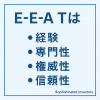2010年頃のアフィリエイトSEOは、
今日の基準で見ると「荒く速い」手法が主流でした。
検索アルゴリズムが単純で、被リンクの量とアンカーテキストが順位を大きく左右した時代。
ここでは当時の代表的な施策を俯瞰し、
現在の視点での評価(使える/グレー/NG)まで整理します。
1. ディレクトリ登録とリンクファーム
Yahoo!カテゴリや各種ディレクトリ、
無料ブログのプロフィール・ブログロールにURLを置くことで、
短期間に被リンクを増やしました。
さらに、相互リンク集やリンクファームを使って量を稼ぐ発想が一般的でした。
- 当時の効果:インデックス促進と初速の順位押し上げ。
- 現在の評価:品質が低いディレクトリは逆効果の可能性。権威ある人手審査型以外は基本NG。
2. EMD(Exact Match Domain)とキーワード詰め込み
「keyword-xxxxx.com」のように狙いキーワードをドメイン名に含め、
タイトル・見出し・本文でも高密度のアンカー語を繰り返す手法が好まれました。
- 当時の効果
関連性シグナルとして強く働いた。 - 現在の評価
EMD優遇は低下。
キーワード詰め込みは読みやすさと品質を損ない、ペナルティリスク。
3. 記事量産とスピニング、サテライト運用
外注と自動スピンで記事を大量生産し、
無料ブログ群(サテライト)から本丸へリンクを送る「リンクホイール」が横行。
PBN(プライベート・ブログ・ネットワーク)で中古ドメインを束ねる形も流行しました。
- 当時の効果:短期的に被リンクと順位を押し上げた。
- 現在の評価:スパム認定・手動対策の対象。長期的な資産化は困難。
4. コメント/トラックバック/ランキング投票の活用
他ブログへのコメント欄やトラックバック送信で
nofollowの壁を回避しつつリンク確保、
ブログランキングの投票ボタンで流入を獲得する小技も定番でした。
- 当時の効果
ニッチでは参照トラフィックを獲得できた。 - 現在の評価
スパム扱いリスク。コミュニティ参加としての交流は有効だが、
リンク目的は逆効果。
5. ページランク・スカルプトと内部リンク最適化
nofollowでのPageRank調整、フッター大量リンク、パンくず最適化、
カテゴリページのテキスト追加など、内部リンクの流れを強く意識する動きもありました。
- 当時の効果:内部で評価を集中させ、上位を取りやすかった。
- 現在の評価:極端なスカルプトは効果薄。情報設計・UX重視の内部リンクは今も有効。
6. ソーシャルブックマークとPing送信
はてな・delicious等のSBM登録、Pingでクローラ呼び込み。
RSS登録サイトへの一括送信ツールもよく使われました。
- 当時の効果:インデックス速度の向上。
- 現在の評価:過剰な自作自演は無意味。SNSからの実トラフィックは有効。
7. テンプレ最適化と広告配置
サイドバー上部の広告、ファーストビューのCTA、
共起語を散りばめた長文、内部リンクの「面」構成は当時から有効で、現在も通用します。
8. 2010年代施策の総括:現代に活かせるポイント
- ①「面」で勝つ情報設計:単発記事ではなく、ハブ&スポークでクラスタ化。
- ②内部リンク=ナビゲーション:ユーザーが解決まで進める導線の設計。
- ③検索意図直球のタイトル:曖昧を避け、悩み・解決・ベネフィットを明示。
- ④速い公開→データで磨く:完璧主義よりPDCA。
9. もう使わない方がよいもの
- スピン記事・自動生成記事の量産
- 品質の低いディレクトリ・相互リンク集
- PBN・中古ドメインの過剰依存
- キーワード詰め込み・隠しテキスト
- 過度なページランク・スカルプト
10. 現代SEOの実務的チェックリスト
- 検索意図(Who/Why/Stage)を見出しに反映
- E-E-A-T:筆者プロフィール・実測データ・参照元を明記
- 内部リンク:導入→詳細→比較→CTAの階層
- UX:スマホ読みやすさ、速度、表・図解の最適化
- 被リンク:実プロジェクト・取材・一次データで自然獲得
まとめ
2010年のSEOは「リンク量×スピード」の時代でした。
現在は「ユーザー価値×信頼性×情報設計」。
当時の学びは無駄ではなく、内部リンクと面作り、検索意図への忠実さ、
PDCAという普遍要素として活きています。
短期的な抜け道ではなく、長期的に積み上がる戦略へ切り替えていきましょう。