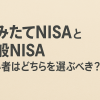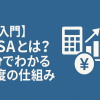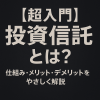新NISAと旧NISAの違いを徹底比較
はじめてでも最短でわかる完全ガイド
2024年から始まった「新NISA」は、旧制度(一般NISA/つみたてNISA)を
抜本的に拡張した“恒久化&非課税枠の大幅増”が特長です。
本記事では、制度の核となる違いを表と要点で整理し、
初心者がいますぐ実践できる使い分けのコツまでまとめます。
まず要点だけ(60秒サマリー)
- 制度が恒久化:新NISAは期限なし。長期前提の資産形成がしやすい。
- 非課税枠が拡大:つみたて投資枠+成長投資枠の2階建てで、年間投資上限が拡大。
- 売却で枠が復活:非課税で売却しても、翌年以降の非課税枠が再利用できる。
- 商品ラインナップの整理:“長期・分散・低コスト”を軸に、初心者はつみたて投資枠中心が王道。
新旧NISAの比較表
| 比較項目 | 旧NISA(〜2023年) | 新NISA(2024年〜) |
|---|---|---|
| 制度の期間 | 有期限(一般NISA:最長5年、つみたてNISA:最長20年) | 恒久化(期限なし) |
| 非課税枠の構造 | 一般NISA/つみたてNISAは“いずれか”利用 | 2つの枠を同時併用(つみたて投資枠+成長投資枠) |
| 年間投資上限 | 一般NISA:120万円/年 つみたてNISA:40万円/年 | 拡大(各枠の上限を合算して利用) |
| 生涯投資上限 | 設定なし | 生涯上限あり(上限内で長期の回転が可能) |
| 売却後の枠 | 売却しても非課税枠は復活しない | 翌年以降に枠が復活(回転が効く) |
| 対象商品 | 一般NISA:幅広い つみたてNISA:金融庁基準を満たす長期向け投信 | つみたて投資枠:長期・分散・低コストの投信等/ 成長投資枠:株式・ETF・投信等 幅広く |
| 運用方針との相性 | 短中期の個別株にも利用可能だが、非課税期間の制約がネック | 長期・積立・分散が前提。売却枠復活でリバランスしやすい |
なぜ新NISAに刷新?(背景と狙い)
少子高齢化・物価上昇のなか、家計に長期投資を根付かせるために
「恒久化」「非課税枠拡大」「売却枠復活」で使いやすさを大幅に改善。
投資デビューの心理的ハードルを下げ、
“貯蓄から投資へ”を一段と後押しする設計になりました。
タイプ別・最適な使い方
① 完全初心者(まずは仕組みに慣れたい)
- つみたて投資枠を中心に、全世界株式や先進国株式の低コスト・インデックス投信を毎月積立。
- 余力が出てきたら、成長投資枠でETFや日本株インデックスを少額追加。
② 既に投資経験あり(分散と税制最適化)
- つみたて投資枠=長期・コア資産/成長投資枠=戦略的サテライトで棲み分け。
- 年1回のリバランス時に売却→枠復活を活用し、非課税のまま比率調整。
③ キャッシュフロー重視(無理なく継続)
- 毎月の積立額は「可処分所得の5〜10%」を目安に。ボーナス月に増額設定も可。
- 一括は避け、時間分散で価格変動リスクを平準化。
旧NISAから乗り換えるときの実務ポイント
- 旧制度の保有資産はそのまま非課税期間まで保有(ロールオーバーの扱いは証券会社の案内に従う)。
- 新NISAではつみたて投資枠を最優先。生活防衛資金を確保し、毎月の積立を継続。
- 投資対象は信託報酬の低いインデックス投信を軸に。迷ったら“全世界株式”の一本化でOK。
- リバランスは年1回。非課税のまま売却→翌年枠復活を活用して比率調整。
新NISAでも避けたいNG運用
- 短期売買の多用:非課税枠の価値を損なう。制度は“長期・積立・分散”前提。
- 高コスト投信の放置:信託報酬の差は年率で地味に効く。コアは徹底して低コストに。
- 毎月分配型の過度利用:複利が効きにくく、長期の資産形成と相性が悪い。
チェックリスト(今日やること)
- □ 証券会社で新NISAの口座区分を確認/申込
- □ つみたて投資枠:全世界 or 先進国株インデックスを選定
- □ 成長投資枠:ETFや株式は“少額・分散”で
- □ 積立日は給与日直後に設定(残高不足を防ぐ)
- □ 年1回の見直し日をGoogleカレンダーに登録